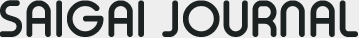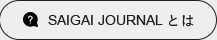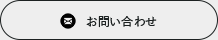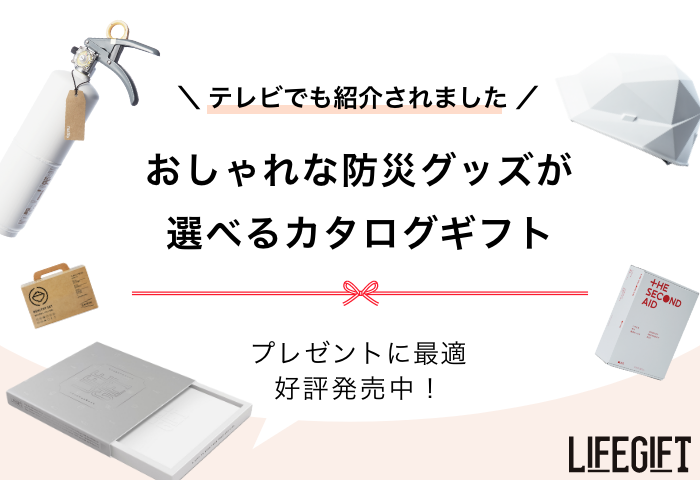最終更新日:2022/09/03 (公開日:2019/02/13)
「顔」


「”表”に出た感”情”」と書いて、「表情」。
言葉の通り、喜怒哀楽などの感情は顔に出る。 震災直後の景色をこの目で見た僕の表情は、ただただ唖然としていたように思える。
東日本大震災では、存ったはずのものが無くなっていた。 家や、畑や、ビルや、お店が、存在していたはずの場所が更地になっていた。津波ですべて流されてしまったのだ。 ただの真っ平らの地面になった”そこ”には、何かが存在していた面影はこれっぽっちも残っていなかった。
だがここ、熊本では違った。
存在していたものが存在したまま、崩れ去っていた。何一つ無くなってはいない。 面影こそあるが、姿形はもはやただの瓦礫でしかなかった。割れてしまった窓のように、激しさを孕んだまま静かに佇んでいる。
そんなことを、熊本県阿蘇に入った車の中で考える。 阿蘇は観光業が主にも関わらず、阿蘇と熊本市内を繋ぐ阿蘇大橋が崩落して通れなくなり、 普段の倍以上の時間をかけて山道を迂回しなければ入れない状況になっていた。 そんな状況もあり、観光客はもちろんのこと、ボランティア自体も少ないので、まったく支援が行き届いていなかった。
阿蘇の内牧という地区に車を止め、情報収集を始める。 どれほどの被害か、困っていることは何なのか、僕たちボランティアが何をすべきなのか。地元の人たちが何をして欲しいのか。
そんな中、一人の男性が僕たちの元へ駆け寄って来た。そして、何かを言った。
これは後から知ることになるが、来てくれたのはその内牧地区の商工会会⻑、Nさんという方だった。
何を言ったのか、覚えていない。たぶん「助けてください」だったんじゃないかと思うが、はっきりとしていない。もはや言葉じゃなかったような気すらしている。それに言葉よりも、その時のNさんの”顔”が忘れられなかった。 当時21歳だった僕が生きてきた中で、たったの一度も見たことがない表情だった。
地域性というのはどこにでもあるものだろう。特に地方だと、その色が濃い場合が多い。 いくらボランティアといっても、地元の人からすれば得体の知れない他所者には違いないのだ。畑を削って高層マンションを建てようとする会社の人たちとなんら変わりがないのだろう。けれど、その得体の知れない余所者にすら助けを求めるしかない状況だった。自分たちだけじゃ、どうしようもなかったのだ。
ほんの少しでいいので、想像してみて欲しい。
まったく知らない他人に「助けてください」と叫ばなければいけないことを。
なりふり構わず助けを求めなければいけない状況に立たされ、様々な感情が入り混じり、ぐちゃぐちゃになったあの表情が、僕の頭にあまりにも鮮烈に残っている。とてもじゃないが、表情なんて呼べるものじゃあなかった。
僕は未だに、あのときの顔を表現する言葉を持ち合わせていない。
その”顔”が、これまで幾度となく僕を奮い立たせてきたのだ。
決して人には見せることのできないような、さみしさや苦しさや責任感や助けを求める叫びや認めたくない思いが、いっしょくたになったあの顔が。
「声にならない声が聴こえた」
手を取ってくれれば、誰でもいいわけじゃない。
しかし、誰かに手を取ってもらわなければどうしようもない状況だったと思う。
今までの人生の中でぼくは、顔も名前もまったく知らない他人に助けを乞うたことはあっただろうか。
助けを乞わないといけなくなったことが、今までにあっただろうか。
ぼくはまったく知らない他人に助けを乞われたとき、どうするだろうか。
(白川 烈 「3.11 つむぐ」熊本地震エッセイ展示より)